体を温める食べ物と冷やす食べ物には何がある?~具体的にご紹介
食べ物には体を温める食べ物と体を冷やす食べ物があります。
温かいものを食べれば体が温まると思いがちですが、食べ物によっては逆に冷やしてしまうこともあるんです。
私たち現代人は体温が低い人が多く、平熱が35度台という人も珍しくありません。 そのせいか「冷え性なのはしょうがないわ」とあまり心配していない人も多いかも。
でも冷えた体は……
- 体内酵素のはたらきが低下
- 新陳代謝も低下
- 免疫力も低下
目覚めが悪い、疲れがとれない、風邪をひきやすい、肌荒れが、などの不調を感じるようになります。
そこで体を温める食べ物にはどんなものがあるか、冷やす食べ物にはどんなものがあるか、その見分け方も含めてわかりやすくお伝えします。
スポンサーリンク
【目次】
温める野菜と冷やす野菜
まずは体を温める野菜と冷やす野菜の見分け方。次に具体的にどんな野菜が体を温めるのか、冷やすのか、ご紹介します。
体を温める野菜と冷やす野菜の見分け方
▼体を温める野菜
- 冬が旬の野菜
- 地面の下にできる野菜
- 黒い色、赤い色、オレンジ色の野菜
▼体を冷やす野菜
- 夏が旬の野菜
- 地面の上にできる野菜
- 白い色、青い色、緑色の葉物野菜
冬が旬の生姜やかぼちゃは温める野菜。夏が旬のナスやキュウリは冷やす野菜。地面の下にできるにんじんやネギは温める野菜。地面の上にできるレタス・ほうれん草は冷やす野菜。
ただし例外も。
トマトは色は赤いですが、南米の暑い地域が原産なので冷やす食べ物。白菜は冬が旬ですが、色が緑色の葉物野菜なので冷やす食べ物。
温めるか冷やすかの見分け方も例外があるので、目安と思ってくださいね。では具体的にどんな野菜があるのか、ご紹介します。
体を温める野菜

- にんじん
- ねぎ
- たまねぎ
- ごぼう
- れんこん
- かぼちゃ
- 生姜
- にら
- にんにく
- にんにくの芽
- 山芋
- ふき
- こんにゃく
- 赤唐辛子
体を冷やす野菜

- レタス
- キャベツ
- 白菜
- ほうれんそう
- 小松菜
- きゅうり
- トマト
- なす
- ゴーヤ
- セロリ
- もやし
- おくら
- 大根
次は果物について、体を温めるものと冷やすものをご紹介します。
スポンサーリンク
温める果物と冷やす果物
果物にも体を温めるものと冷やすものがあります。
果物はバナナ、パイナップル、マンゴーなど暑い南国産のものが多いので体を冷やしてしまいがち。でも、温めるものもあります。
体を温める果物と冷やす果物の見分け方
温める果物と冷やす果物の見分け方は、
- 寒い地方でとれる果物は体を温める
- 暑い地方でとれる果物は体を冷やす
では具体的にどんな果物があるのでしょうか。
体を温める果物
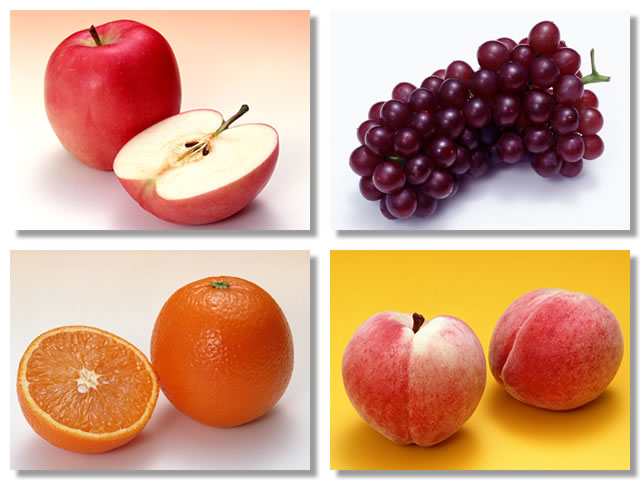
- りんご
- ぶどう
- さくらんぼ
- オレンジ
- いちじく
- あんず
- 桃
- プルーン
りんごは青森や長野など寒い地域でとれるので温める果物。オレンジは温かい地域でとれるので体を冷やすイメージがありますが、血行をよくしたり、体を温めて汗を出して風邪の熱を下げるはたらきがあるんです。
体を冷やす果物
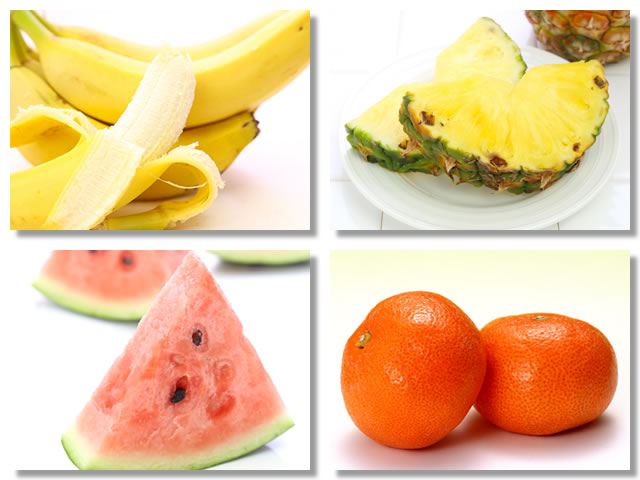
- バナナ
- パイナップル
- マンゴー
- すいか
- みかん
- レモン
- グレープフルーツ
- 柿
- キウイ
- メロン
- 梨
冷やす果物だからといって敬遠することはありません。果物には酵素もたっぷり含まれていますし、マンゴーやパパイヤなどの南国の果物は抗酸化作用にもすぐれています。
そこで「果物と一緒に体を温める食べ物や飲み物をとる」というのがおすすめ。
コーヒーのかわりに生姜湯や紅茶を飲む。白いパンのかわりに全粒粉のパンを食べる。食事に納豆・キムチ・漬物・味噌といった発酵食品を加える。
ひと工夫して、体を温める食べ物や飲み物を取り入れてみてくださいね。
次は、調味料、魚、お肉、について温める物と冷やす物をお伝えします。
温める調味料と冷やす調味料
調味料にも体を温めるものと冷やすものがあります。
味噌、しょうゆ、塩といった調味料は、量は少なくても毎日食べ続けているもの。体を温める調味料をとるように心がけたいですね。
体を温める調味料と冷やす調味料の見分け方
- 塩からい調味料は体を温める
- すっぱい調味料は体を冷やす
ではどの調味料が温めるのか、冷やすのか。「ごはんのお供」も含めて紹介します。
体を温める調味料・ご飯のお供

- 塩
- 黒砂糖(黒糖)
- 味噌
- しょうゆ
- ラー油
- 唐辛子
- 明太子
- ちりめんじゃこ
- 佃煮
発酵食品である味噌やしょうゆは体を温める食べ物。寒い冬にはキムチ鍋や担々麺などのからい料理が食べたくなりますが、唐辛子が体を温めてくれるから食べたくなるのではないでしょうか。
体を冷やす調味料・ご飯のお供

- 白砂糖
- 酢
- マヨネーズ
- ドレッシング
- 化学調味料など
暑い夏にサッパリと酢の物を食べたくなりますね。これはお酢が暑い体を冷やしてくれるから自然と食べたくなるのです。
スポンサーリンク
体を温める魚と冷やす魚
魚にも体を温めるものと冷やすものがあります。
ただ、全般的には体を温めるものが多く、特に寒い北の海で獲れる魚や赤身の魚は温めるはたらきが強いようです。
見分け方はこちら。
- 北の海で獲れる魚や赤身の魚は体を温める
赤身の魚は温めるはたらきが強いとはいえ、白身の魚が体を冷やすかというとそうではありません。温めることも冷やすこともない「中間の食べ物」です。
体を温める魚

- 鮭
- まぐろ
- かつお
- サバ
- イワシ
- さんま
- カニ
- ほたて貝
- 明太子
- ちりめんじゃこ
- 海藻
鮭は寒い北の海で獲れるもの。かつおは赤身の魚。明太子は塩辛い。ということで体を温める食べ物になります。
青魚、ちりめんじゃこ、海藻など手軽で身近なものも多いので、食事に取り入れやすいですね。
体を冷やす魚

- うなぎ
- はも
- あさり
- しじみ
- ウニ
温める肉と冷やす肉
お肉も魚と同じで、白身よりも赤身の方が温めるはたらきが強いです。
肉でいう「白身」はおもに「脂肪」の部分。寒い地域でよく食べられているお肉は温めるはたらきが強いですね。
体を温める肉

- 羊の肉(ラム)
- 鹿の肉
- 牛肉
- 鶏肉
- 鶏のレバー
- 赤身の肉
ラムといえばジンギスカン、といえば寒い北海道。寒いモンゴル地方でもラム肉が好まれてきたのは、温めるはたらきがあったからなのでしょう。
体を冷やす肉

- 豚肉
全般的には温めるはたらきをするお肉ですが、その中で豚肉が冷やす傾向にあります。
沖縄で料理に豚肉が広く使われていたり鹿児島で黒豚が有名なのも、温かい地域の人の熱い体を冷やしてくれるはたらきがあるからかもしれません。
飲み物にも体を温めるものと冷やすものがあります。こちらでくわしく紹介しています。
体を温める飲み物、冷やす飲み物には何がある?具体的にご紹介!
以上、体を温める食べ物と冷やす食べ物をお伝えしました。
体を冷やすものはダメ、ということではありません。
栄養価が高い、抗酸化力が高い、酵素がたっぷりなど、食べ物にはそれぞれ特性があります。特性を理解してバランスよく食べるのが一番ですね。
さて、疲れがとれない、体が重たい、体調がいまひとつ……というあなた、肩こり、背中がカチカチ、体が固くなっていませんか?
マッサージされると体が軽くなるように、体をほぐせばぐんぐん元気に楽になります。
そこで自分で深く体をほぐす方法をご紹介。自宅で簡単、誰でもすぐできる方法ですので、ぜひ試してみてください。
ゆるめて軽い体になる方法とは? >>
*-*-*-*-*

この記事の執筆者:
株式会社ナチュラルハーモニー代表 斉藤豊
1995年から栄養補助食品の販売業務をきっかけに栄養学を学ぶ。以来、健康食品・健康器具など10年の業務経験とともに自律神経など体のしくみを学び、2006年に健康通販(株)ナチュラルハーモニーを設立。
リラックスジェル「プアーナ」、内科医・医学博士の堀田忠弘先生考案・監修「野菜力で輝け」、医学博士の吉村尚子先生開発の和漢の健康茶「浄活茶」など天然由来成分100%の健康商品を販売して今年で18年目を迎える。※執筆者プロフィールはこちら
*-*-*-*-*
スポンサーリンク
